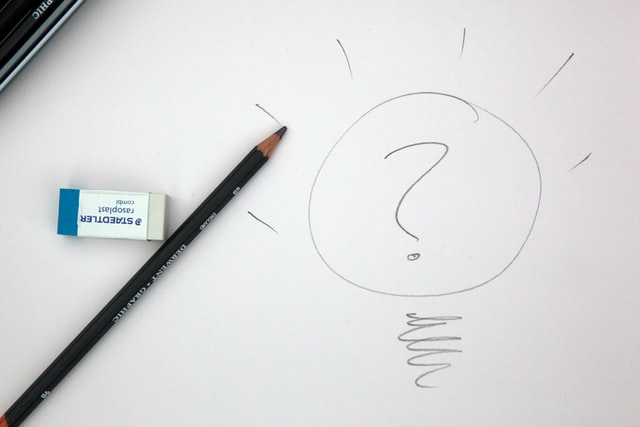いつも読んで頂きありがとうございます。
今回は、調節性内斜視の分類についてです!
学生時代を振り返ると、斜視の勉強は奥が深く、水平斜視・上下斜視・回旋斜視についてやっと理解ができたと思ったら、さらにその先に斜視の分類まであることを知り、衝撃を受けたことを今でも覚えています。
今回は、調節性内斜視の分類について、その中でも屈折性調節性内斜視と非屈折性調節性内斜視の2つをメインに話を進めていきます。この記事を読み終えた時に、「調節性内斜視の分類」を暗記ではなく、理解して覚えられたと感じて頂けるように書いていきます!
※視能学 第2版p357-359を参考に内容を書いていますので、定義を確認しながら勉強される方はそちらも見ながら読んで頂くと良いです!
なぜ調節性内斜視の分類が難しく感じるのか?
『各型が漢字のみ・同じような名称で、さらに1つ1つの名称が長いから』
私はこのような理由で難しさを感じていました。
調節性内斜視の分類は、4つの型があります。
①屈折性調節性内斜視
②非屈折性調節性内斜視
③非調節性輻湊過多型内斜視
④部分調節性内斜視
これが各型の名称となります。これを学生時代に初めて見た時は、本当に戸惑いました。漢字ばかりで長いし、同じような名前でもう何が何だかわかりませんでした(笑)
一見、難しそうに見えるこの4つの型ですが、考え方がわかっていれば、暗記ではなく理解して覚えることができます!以下で解説をしていきます!
前提として、ここを押さえる!
この後、調節性内斜視の各型の解説を行っていく上で、「近見反応」と「AC/A比」を事前に理解して頂いていることで内容がよりわかりやすくなるので、先にこの2つを説明していきます。
近見反応で3つのことが起こる
「近見反応(近見反射)」については、ご存じの方も多いと思いますが、1人でも多くの方に内容を理解して頂くために書かせて頂きます。
近見反応(近見反射)とは、近くを見るときに、輻湊とともに調節と縮瞳が起こるというものです。1)
つまり、調節をすると、輻湊と縮瞳も一緒に起こることになります。
1)所敬. 現代の眼科学改定第12版. 金原出版, 2015 ,66.
AC/A比ってそもそも何なのか?
AC:accommodative convergence(調節性輻湊), A:accommodation(調節)の略語となります。
つまり、AC/A比は、1Dの調節に対する調節性輻湊を表したもの。輻湊はプリズム(△)、調節はdiopter(D)で表されるため、AC/A比の単位は△/D(プリズムジオプトリー)となります。
18か月頃には、通常のAC/A比が成立していると考えられており、正常値は2~6△/Dです。2)
2)丸尾敏夫. 視能学第2版. 文光堂, 2014 ,191.
今後、記事にまとめる機会があればまとめてみます。
まずは、この2つの型を理解しよう!
いよいよここから調節性内斜視の詳しい内容に入っていきます。先ほど説明した 「近見反応」と「AC/A比」 の考え方も使って解説をしていきます!
各型を理解するために重要なのは、「屈折性調節性内斜視」と「非屈折性調節性内斜視」を理解することです。
この2つの型が理解できれば、残りの「部分調節性内斜視」と「非調整性輻湊過多型内斜視」はすぐに理解できるようになりますので、先にこの2つの型の説明をしていきます!
屈折性調節性内斜視
屈折性調節性内斜視(refractive accommodative esotropia)とは、遠視があるため裸眼で明視をしようとして調節をかけた際に内斜視を引き起こすもの。遠視の度数は+2.0D~+8.0Dで、AC/A比は正常です。
まだわかったようなわからないような感じだと思いますので、もう少し書いていきます!
遠視度数が中等度以上あるため、裸眼で物を見ようとすると、調節を多くかける必要がある!AC/A比は正常だが、明視するために必要な調節量が多いため、その分輻湊が起こり、内斜視になってしまうということ!
<まとめ:屈折性調節性内斜視を理解して覚えるための考え方>
屈折性→中等度以上の遠視があり、裸眼で生活をしている。
調節性→裸眼で明視するために調節をかける。
つまり、中等度の遠視がある場合に裸眼で生活をしていると、調節量が多いことで眼が内によってしまう。→これが屈折性調節性内斜視の考え方。
治療については、遠視度数が関係しているためアトロピンテストを行い、完全矯正眼鏡を処方することになります。眼鏡装用をして斜視角が改善するか経過をみていきます。
非屈折性調節性内斜視
非屈折性調節性内斜視(nonrefractive accommodative esotropia)とは、AC/A比が高いために生じる内斜視で、近見の斜視角が遠見より10△以上大きいもの。
屈折異常がある場合、完全矯正下で遠見斜視角は消失するが、近見で内斜視が残る。
ただし、近見眼位測定時に+3.0Dすると斜視角が減少する。→近見時に調節をかける必要がないため。
1Dの調節(A)に対する調節性輻湊(AC)がかかりすぎることで近見で内斜視となっている!
つまり、AC/A比が正常値より、高値となっている状態。→だから、非屈折性調節性内斜視は「高AC/A比型内斜視」とも呼ばれるということになります。
いま、さらっと書きましたが、非屈折性調節性内斜視には「高AC/A比型内斜視」という別名があり、別名があるということも難しいと感じる原因だと思います。
ただし、この別名については上記した非屈折性調節性内斜視の考え方を知っていれば、それをただ別の言い方で「高AC/A比型内斜視」と言っているだけということをここまで読んで頂いている方には理解して頂けたと思います!「非屈折性調節性内斜視=高AC/A比型内斜視」ということになります。
<まとめ:非屈折性調節性内斜視を理解して覚えるための考え方>
非屈折性→”非”のため、屈折度は関係ない。つまり正視・近視・遠視でも起こる可能性はある。(中等度の遠視が最も多いとされる)
調節性→非屈折性のため、近見時の調節のこと。
つまり、正視or完全矯正下で、屈折の要素を取り除いても、AC/A比が高値のために近見で内斜視になってしまう。→これが非屈折性調節性内斜視(高AC/A比型内斜視)の考え方。
治療については、アトロピンテストを行い、完全矯正の近用部に+3.0D程度の加入をした二重焦点眼鏡を処方して経過をみていきます。
少し余談になりますが、事前に、屈折性調節性内斜視を防ぐことも視能訓練士として大事な仕事となります!遠視度数によっては、裸眼で視力・眼位・立体視が良好でも眼鏡処方を行う必要があります。私のオンライン勉強会の題材にしていますので、ぜひ参加して頂ければと思います!

ここまでの内容が理解できたらあと少しです!
上記した2つの型が理解できれば、調節性内斜視の分類を理解して覚えられるまであと少しです!先ほど紹介した考え方を使って、残りの「非調節性輻湊過多型内斜視」と「部分調節性内斜視」について解説をしていきます!
非調節性輻湊過多型内斜視
いきなり結論を書きます!
『非屈折性調節性内斜視を疑い、近用加入しても近見の斜視角が減らないもの』
これが非調節性輻湊過多型内斜視となります。まだわかりにくいと思うので、まとめてみます。
この型は、”非調節性”のため、調節性輻湊ではなく、近接性輻湊(物が接近することによる輻湊)によって内斜視となるものです!
つまり、非調節性輻湊過多型内斜視では、完全矯正度数に+3.0Dをして、調節要素を取り除いても近見で内斜視が残るということになります。
非屈折性調節性内斜視を疑い、cc+3.0Dしても近見の斜視角が減少しない型が非調節性輻湊過多型内斜視というイメージです!
部分調節性内斜視
これも結論から書きます!
『調節性内斜視として眼鏡装用を行い、3ヶ月以上経過しても遠近ともに内斜視が10△以上が残るもの』
調節性内斜視の治療として眼鏡装用するも、遠近ともに10△以上内斜視が残ってしまうものを部分調節性内斜視として考えて頂くと良いと思います!
最後に
今回は、調節性内斜視の分類についての考え方を書いてみました!なるべく簡潔にわかりやすく分類を理解して頂くために、各型の予後や治療法までは詳しく書けていないので教科書などを参考に勉強して頂ければ思います。
視能訓練士に関する勉強は、一見暗記するしかないように思えるものの考え方を知っていれば理解して覚えられる内容がたくさんあると感じています。(Bagolini線条試験や、Maddox double rod testなど)
興味のある方は私が行っているzoom勉強会に気軽にご参加下さい!
<参考文献>
丸尾敏夫. 視能学第2版. 文光堂, 2014 ,357-359