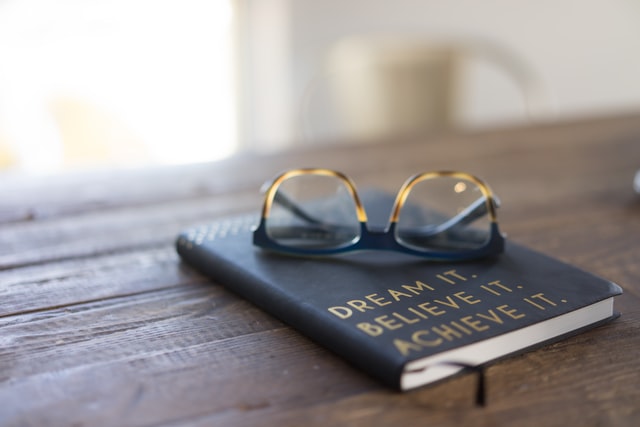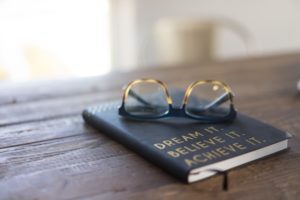今回は、眼鏡処方を難しいな・苦手だなと感じている若手ORTの方に向けて処方のポイントをまとめてみました。
私は眼鏡処方を行う際、「①最高視力がどこまで出るのか(度数調整も含めて)」、「②患者さんのニーズを聞く力」、「③そしてそれに合わせた提案」ということを意識して処方を行っています。
視能訓練士としての知識を生かして、検査を行い、患者さんに納得して頂ける眼鏡を処方するためには、検査手技と同じくらいコミュニケーションの取り方が重要だと感じています!
そこで、今回は「検査手技編」、次回の記事で「コミュニケーション編」という形で、2つに分けて書いていきます。
※今回の内容は、視能訓練士の方・眼科で働く方に向けた内容となります!
眼鏡処方が難しいと感じる理由
はじめに、眼鏡処方が難しいと感じる理由について考えていこうと思います。
「最高視力を出すこと・完全矯正度数を導くことが難しい」、「度数の調整方法がわからない」、「乱視や不同視だとわからなくなる」、「時間がかかりすぎる」など、この他にも人によっていろいろと理由があると思います。
理由がわかっているということは→自分が難しいと感じていることを克服できれば、眼鏡処方がどんどん上手くなると僕は考えています!
当たり前!と思われた方がおられると思いますが、若手ORTの方の中には、眼鏡処方に対してなんとなく苦手意識がついている方もおられると思い、まずは自分が何に難しさを感じているかを考えてもらいたくてこのような書き方をしています。
問診→検査ではなく、検査→問診!
みなさんは、問診と検査はどちらを先にされていますか?
僕は、検査→問診の順で行っています。先にその日の眼鏡合わせに必要なデータを集めて、その検査結果を元に問診・レンズの相談を行う方が効率が良いかなと感じています。
なぜか?→先に問診を行う場合は、検査前と検査後に2回も話を行うことになり、時間がかかってしまう!検査前の問診は、初診ならデータなし、再診なら前回データで行い、検査後に当日測定した検査データを元にもう一度同じような話をすることになります。
前回データと当日の検査結果が異なる場合にも有用です。→この場合、検査前の問診と検査の後の問診の内容が変わります。前回データより、当日が結果が悪い場合は、最初に伝えた結果より悪い値を伝えることになるので、患者さんが不信感を抱く可能性がある。
※ある程度進行した糖尿病網膜症(DR)や点状表層角膜症(SPK)などの疾患では、短い期間で視力が変動することがあり、以前より当日の矯正視力が悪くなっていることが多々あります。
※今回の内容は検査手技なので、ここでは、検査→問診の順で行うことを頭に入れて頂くだけでOKです。聞き方・提案など問診の仕方は、コミュニケーション編で詳しく解説します!
【1番重要】とにかく遠見の完全矯正をきっちり行う!
眼鏡合わせは、遠見の完全矯正度数がきちんと測定できることが重要です!→とにかくこれに尽きます!
度数調整する際や、近用度数を決める際などは、すべて遠見の完全矯正度数を参考に調整していくことになります。
矯正視力良好の近視や乱視、不同視などの場合は、眼鏡処方をする上で完全矯正ではなく、等価球面値で置き換えたり、度数を調整したりして処方をすることがありますが、すべて完全矯正値を出した上での話になりますので、「まずは過矯正・低矯正なくきちんと完全矯正度数を測定する!」ということを意識しましょう!
以下で、きちんと完全矯正度数を導くためのポイントを紹介していきます。
①裸眼視力を参考に
完全矯正度数を求める際に、レフ値はもちろん参考にしますが、それに加えて裸眼視力も参考にすることができます。
『完全矯正度数と裸眼視力の関係性を意識する!』
この関係性がわかれば、レンズのファーストチョイスが圧倒的に上手くなります。→視力検査が上手になるので、結果的に眼鏡合わせを行う上での手技も上達することになります。
裸眼視力の考え方を知りたい・勉強したいという方は以下にリンクを貼っていますので、ぜひ一緒に勉強をしましょう!

②乱視がある時は、ケラト値も見よう!
乱視の矯正を行う上で、よく聞くフレーズは、「レフ値で表示されているシリンダー度数より、少なめの度数から始める」というものではないかと思います!
これも乱視矯正の1つの方法だと思いますが、一概に全ての症例で乱視を少なめから始めるというのはどうなの?と思われている方もおられると思いますので、今回は、もう1つの方法を紹介します!
『レフ値だけでなく、ケラト値も見る!』
ケラト値で表示される乱視=角膜乱視となり、レフで乱視が検出された場合、角膜乱視も強いと乱視度数はしっかり入れた方が視力が出やすく、角膜乱視が弱い場合は少なめの乱視度数で視力が出るかなという印象です。
わかったようなわからないような感じだと思いますので、例を出してみます!
※わかりやすくなるよう右眼のみで話を進めていきます。
[レフ値]
<R> SPH CYL Axis
1 -0.5 -2.50 180 9
2 -0.5 -2.50 180 9
3 -0.5 -2.50 180 9
< -0.5 -2.50 180 >
上記のレフ値に対して、以下でケラト値の例を2つ提示して解説をしていきます!
上記のようにレフで中等度の乱視が検出されたとします。乱視の眼に対して完全矯正を試みる際、「とりあえず少なめにレフ値から1.0D程度減らした度数から始める!」という方が多いと思いますが、ここでケラト値を見ることもおすすめです。
角膜乱視も強ければ、完全矯正する際にある程度の乱視度数がいるかなと判断する・角膜乱視が少なければ乱視度数はそんなに入れなくても良いかなと判断する!
例1)ケラト値の乱視(角膜乱視)が弱い場合
[ケラト値]
<R> mm D deg
R1 7.49 45.00 180
R2 7.34 46.00 90
AVG 7.42 45.50
CYL -1.00 180
※この際にレフ値の乱視軸とケラト値の乱視軸が一致しているかも確認しておくと良いです!
例2)ケラト値の乱視(角膜乱視)が強い場合
[ケラト値]
<R> mm D deg
R1 7.98 42.25 180
R2 7.50 45.00 90
AVG 7.74 43.50
CYL -2.75 180
レフ値で検出された乱視量は2.5Dです。例1は角膜乱視が1.0Dなので、シリンダーのファーストチョイスは1.0D程度を選択します。例2は角膜乱視が2.75D程度なので、シリンダーのファーストチョイスは1.5~2.0Dを選択します。
このようにレフでの乱視量が2.5Dでもケラトによってレンズのファーストチョイスを変えていく方法も実践して頂くと手技の幅が増えると思います。
乱視は裸眼で見ると「ブレる・ダブる」と感じるため、乱視の度数調整は、矯正視力測定時に患者さんにブレる感じが残っていないか確認することも1つの手です!ブレが残っていなければ、乱視の矯正はできているかなという1つの目安になります。
※白内障など、眼疾患が原因で単眼複視(ブレ・ダブり)を感じることもありますので、レンズで矯正できないブレがあることを覚えておくことも大事です。
※ここで記載した乱視は、不正乱視がなく矯正視力良好なものとします。
③眼鏡を持っていれば度数を測定
角膜疾患、白内障、硝子体混濁などによって、中間透光体に混濁があると、レフ値の信頼性が落ちます。
慢性的な角膜疾患(円錐角膜・角膜ジストロフィなど)ではレフの信頼性は低いなかで眼鏡合わせをすることもあります。レフがあまり当てにならない場合は、眼鏡度数を参考にする!
眼鏡度数がレフの役割をしてくれて、スムーズに完全矯正できる場合があります。眼鏡度数を確認することは、完全矯正度数を導く上でも重要ですし、乱視・不同視がある場合の処方度数の決定にも役立ちます。赤線部の詳しい説明は、以下の「見えやすさとかけやすさ」の項で詳しく説明します。
残余調節力を頭に入れておく!
処方する眼鏡を近用でも用いる場合は、年齢ごとの残余調節力を頭に入れておき、必要に応じて加入度数を決定していくことになります。表にまとめます。
表 年齢別の残余調節力 (文献1を参考に作成)
| 年齢(歳) | 調節力(D) |
| 10 | 12 |
| 20 | 9 |
| 30 | 6 |
| 40 | 4 |
| 50 | 2 |
| 60 | 1 |
※IOL眼、無水晶体眼は調節力は0Dとなります。上記の数値はあくまで目安で、たまに残余調節力が目安より弱まっている患者さんもおられるのでそこは注意が必要です!
1)所敬. 現代の眼科学改定第12版. 金原出版, 2015 ,65.
以下の記事で、残余調節力、老眼(老視)について詳しく解説をしています。

見えやすさとかけやすさ
・外来での視力検査は最高視力を出すために完全矯正を行う。
・眼鏡処方時は完全矯正を行った後、「見えやすさを保ちつつ、かけやすさ」を考慮して度数を調整する。
上記したように、眼鏡処方時は、両眼開放時の装用感(かけやすさ)も意識して度数調整を行うことになります。
かけにくい眼鏡度数としてよく聞くのは、乱視や、不同視が多いと思います。乱視度数は2.0D程度まで、度数差も2.0D程度が一般にかけられる度数の上限とされることが多いと思います。
考え方としては、完全矯正度数に近い度数ほど、片眼ずつの見え方は良くなる。その患者さんがかけられる度数の範囲内で、必要な見え方を患者さんと相談しながら、処方度数を考えていく!
かけられる度数なのかを考える際に、現在の眼鏡度数がとても参考になります!→イメージがしにくいと思うので、乱視症例で説明をしていきます。
※処方度数が決まったら、両眼視力も測定すると思いますが、ここでは説明の都合上両眼視力の記載は省略しています。
例)25歳男性 以下に完全矯正度数を示します。
※説明がわかりやすくなるよう右眼のみ記載します。左眼は右眼と全て同じ値とします。
RV=0.5(1.5×C-2.0DAx180°)←完全矯正度数。
RV=(1.0×S-0.5D=C-1.0DAx180°)←等価球面で乱視を調整した度数。
上記の検査結果だったとして、2パターンの例を出して解説します。
例1)JB度数:B)S-1.5D=C-0.5DAx180°を装用中。
RV=(0.7×JB)、LV=(0.7×JB)、BV=(0.8)
主訴:遠くがぼやけて見えるからもう少し見え方を良くしたい。
→JBで遠くの見えにくさを感じているので、度数を調整する必要がある。JBの乱視度数が0.5Dのため見え方を重視して、乱視度数を上げすぎると、頭痛やクラクラした感じを引き起こす可能性がある。そのため、上記した等価球面度数付近での度数を提案し、患者さんと相談を行う。
例2)JB度数:B)C-3.0DAx180°を装用中。
RV=(0.7×JB)、LV=(0.7×JB)、BV=(0.8)
主訴:遠くがぼやけて見えるからもう少し見え方を良くしたい。今の眼鏡にきつさは感じていない。
→JBの情報はとても有効です。乱視が3.0DのJBできつくないなら、乱視度数は2.0Dでもまったく問題がないと考える。この場合は、見え方を重視して、上記した完全矯正での度数を提案し、患者さんと相談を行う。
※「見えやすさとかけやすさ」について理解が深まるようこのような例の出し方をさせて頂いています。
※今回の例は25歳のため、近見視力は確認していませんが、40歳代以降では近見視力を測定することも重要です。
この2つの例のように、完全矯正度数が同じ場合でも、患者さんの状況に応じて処方度数を変えていくことになります。
眼鏡処方は時間をかけすぎないことも大事
現在、眼鏡処方に難しさを感じている方に、所要時間のことについて書くべきか迷いましたが、1つ伝えておきたいことがあるので書かせて頂きます。
施設によって眼鏡処方にかけられる時間が異なるということです。→僕がいた大学病院では眼鏡枠というものがあり、1時間かけて眼鏡合わせをしていました。現在、勤務している個人眼科はバタバタした外来の中でなるべく時間をかけず、かつ患者さんに満足してもらえる眼鏡合わせをしています。
僕の感覚では、1時間かけてというより、最小限の時間で良い眼鏡処方を行う眼科が多いかなという印象です。そのため、早く正確に眼鏡処方を行えるというスキルを身に付けておくと、転職の際などにアピールポイントになると思います!
最後に
様々な考え方があると思いますが、僕が普段意識していることを書いてみました。
1つの考え方として参考にして頂き、他の考え方も参考にしながら、自分なりにどんどん付け足して頂くと眼鏡処方が上手くなると思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
眼鏡処方のコミュニケーション編はこちら↓